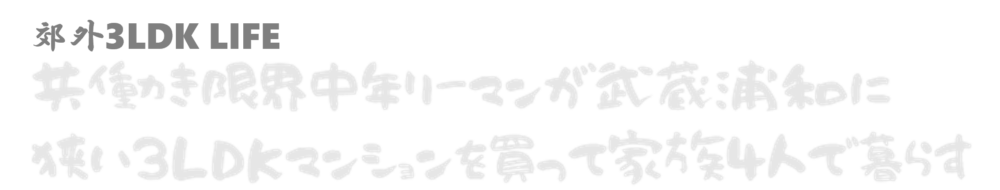本論考は、「都心タワマンが栄華を誇る一方で、郊外マンションに“次の夢”は残されているのか」という問いを手がかりに、郊外マンションは本当に“オワコン”なのかを考える試みである。前回は、この問いに向き合うにはまず歴史的な文脈を押さえる必要があると考え、東京とその周辺がどのように人々に住まわれ、住宅供給や人口移動の変化を通じて現在の都市構造が形づくられてきたのかを整理し、議論の出発点とした。今回はその続きとして、終戦直後の深刻な住宅難をひとまず脱した後の時代から、話を進めていきたい。
首都圏の住宅供給史(3) -団地革命-
2DKが「家族の形」を書き換えた日
「ダイニングキッチン」という発明、あるいは生活の近代化
戦後、焼け野原からの復興期にあった日本は、深刻な住宅不足という国家的課題に直面していた。都市部への急激な人口集中と住宅難を解消するため、政府が切り札として打ち出したのが、公的住宅団地(いわゆる「団地」)の大量供給である。
1955年に日本住宅公団(現・UR都市機構)が発足し、その翌年の1956年、大阪府堺市において公団住宅第1号となる「金岡団地」が竣工する。全900戸に及ぶこの団地で起きた革命、それこそが「2DK」の間取りと「ダイニングキッチン(食堂付き台所)」の採用である。
それまでの日本の伝統的な家屋において、「食事専用の部屋(食堂)」という概念は希薄であった。畳の部屋にちゃぶ台を出して食事をし、終われば片付けて布団を敷くという、空間を多目的に使う生活が当たり前だったのである。しかし、団地の登場によって、「椅子に座って食事をし、寝室とは明確に分ける」という生活様式、いわゆる「食寝分離」が標準化された。
住まいの設計が変われば、そこでの家族の振る舞いも、家事のあり方も変わる。その意味で、団地は単なる物理的な住宅供給にとどまらず、日本人の生活そのものを強制的に「近代化」させる巨大な「装置」として機能したのである。
首都圏の巨大団地群と、新しいライフスタイル
この「団地革命」の波は、すぐさま首都圏へと波及する。 1957年以降、千葉県柏市の光ヶ丘団地(約1,000戸)を皮切りに、豊四季台団地(4,666戸)、松戸市の常盤平団地(4,839戸)など、数千戸規模のマンモス団地が次々と建設された。
水洗トイレやステンレス流し台、そしてダイニングキッチンを備えた当時の団地は、庶民にとって最先端の「憧れの住まい」であった。そこで展開される「椅子とテーブル」の生活は、戦後日本人が脱却しようとした古い因習からの解放を意味し、新しい中流階級のアイデンティティとなっていったのである。こうして団地は、高度経済成長期の風景を決定づける象徴的な存在として、日本の都市郊外にその根を下ろしていった。
首都圏の住宅供給史(4) -郊外庭付き一戸建-
「いつかはマイホーム」が国民的悲願になった日
「庭付き一戸建て」が“到達可能な夢”へと変わる
戦後の住宅不足を「団地」が埋めた後、高度経済成長期に入ると、住宅市場は新たなフェーズへと移行する。その原動力となったのが、国民所得の著しい増加と、住宅ローン制度の整備である。
これら経済的・制度的な基盤が整ったことによって、それまで一部の富裕層にとっての高嶺の花であった「庭付きの郊外一戸建て住宅」は、一般の勤労者層(サラリーマン)にとっても「到達可能な夢」へと劇的な変貌を遂げた。住宅取得のハードルが下がったことで、マイホームを持つことは単なる憧れではなく、多くの家庭が現実的に目指せるライフプランの核心として定着していったのである。
「現代住宅双六」が描いた幸福のテンプレート
この劇的な価値観の転換を、最も象徴的に表しているのが、当時の新聞紙面を飾った「現代住宅双六(すごろく)」(朝日新聞 1973年1月3日掲載)だ(下図)。

(朝日新聞 1973 年 1 月 3 日掲載)
- この双六では、人生の成功モデルが極めて分かりやすく視覚化されていた。
- スタート:木造アパートや借家での生活
- プロセス:ボーナスで頭金を貯め、銀行ローンを組む
- ゴール(上がり):郊外の庭付き一戸建てを購入
この双六が社会に提示したのは、単なる住み替えの手順(ハウジング・ラダー)ではない。庭付きの持ち家を手に入れることが、安定した家族生活の象徴であり、ひいては「一人前の市民としての社会的成熟(=家族の幸福)」を示すものであるという社会的規範(ノルム)であった。人々はこのレールに乗ることを疑わず、その「上がり」を目指してこぞって郊外へと移動を開始したのである。
郊外を埋め尽くす「プレハブ」と均質なコミュニティ
この爆発的な「マイホーム需要」に応えるために登場したのが、多摩ニュータウン(1971年入居開始)や港北ニュータウンといった公的・民間の大規模開発と、それを支える「プレハブ住宅」の技術革新である。
プレハブ住宅とは、住宅の構造部材や内装部品の多くを、現場ではなく工場で事前に製造(prefabricated)し、現地で組み立てる工法の住宅を指す[7]。ハウスメーカー各社はこの手法を採用し、マイホームを一種の「パッケージ商品」として大量供給することを可能にした。
その結果、郊外に出現したのは、同一世代・同一階層(年収や家族構成が似通った人々)が一斉に入居する、画一的で均質なコミュニティ、いわゆる「パッケージ・サバーブ(郊外住宅地)」であった。こうして、東京圏の人口はドーナツ状に外縁部へと急速に拡大し、現在に続く首都圏の都市構造の原型が形成されていったのである。
首都圏の住宅供給史(5)-マンションの発明-
「空中の権利」はいかにして「資産」となったか?法と欲望が交錯する黎明期
区分所有法(1962年):市場を創出した「法的大転換」
郊外へ向かう「戸建て」の拡散と並行して、都心部では静かに、しかし革命的な動きが始まっていた。「分譲マンション」の登場である。
日本初の民間分譲マンションとされるのは、1956年に東京都新宿区で日本信販によって分譲された「四谷コーポラス」だ。しかし、この時点ではまだ「マンション」という法的概念は確立されていない。当時は、建物の権利関係が曖昧であり、今日のように住戸単位で自由に売買したり、抵当権を設定したりすることは困難であった。いわば、黎明期のマンションは「海のものとも山のものともつかない」存在だったのである。
歴史を決定的に変えたのは、1962年に制定された「建物の区分所有等に関する法律(建物区分所有法)」である。 この法律こそが、日本の都市居住における最大のイノベーションであったと言っても過言ではない。なぜなら、この法律によって初めて、一つの建物を複数の所有者で区切って所有する仕組みが制度的に認められたからだ。これにより、「建物の空中権」が法的に切り分けられ、マンションは単なる「共同生活の場」から、登記可能で流動性のある明確な「不動産資産」へと昇華したのである。
資産価値が法的に裏付けられたことの意味は大きい。それはすなわち、マンションが銀行融資(住宅ローン)の担保対象になり得ることを意味し、人々がローンを組んでマンションを購入するという、現代では当たり前の市場メカニズムの前提条件がここに整ったのである。
「第一次マンションブーム」と「億ション」の衝撃
法整備と呼応するかのように、1964年の東京オリンピック景気が市場を刺激し、都市開発と相まって「第一次マンションブーム」と呼ばれる局面が到来する。
ここで注目すべきは、郊外と都心の明確な「性格の分離」である。当時、郊外で供給されていた「団地」が、住宅不足を解消するための実用的かつ大衆的な住まい(2DKなど)であったのに対し、民間事業者が手がける都心の分譲マンションは、当初から「高級感」を訴求する商品として展開された。
その象徴にして頂点とも言えるのが、1964年、オリンピックイヤーに原宿駅前(渋谷区神宮前)で分譲された「コープオリンピア」(売主:東京コープ)である。 ホテルのようなフロントサービスやセントラルヒーティングを備えたこの物件の分譲価格は、当時としては破格の3,000万円から最高1億円に達した。現代の貨幣価値に換算すれば、数億円から十数億円規模のインパクトであろう。これが日本初の「億ション」として世に知られることとなり、「都心マンション=資産価値・ステータス」という、現在まで続く日本独特のマンション観(図式)を決定づけたのである。
制度(区分所有法)が市場の土台を作り、イベント(五輪)と象徴的物件(コープオリンピア)が人々の欲望に火をつける――。こうして1960年代、日本のマンション市場は、単なる住居の確保を超えた「資産形成とステータスの舞台」として、華々しくその幕を開けたのであった。
首都圏の住宅供給史(6) -タワーマンション登場-
都市の欲望は「垂直方向」へ。規制緩和が導いた摩天楼の時代
高さ制限撤廃と、埼玉から始まった歴史
タワーマンションの歴史は、日本の都市計画における「規制緩和」の歴史そのものである。 かつての建築基準法には、市街地における建物の高さを一律で制限する「高さ31メートル制限(およそ10階建て相当)」が存在していた。しかし、1963年の特定街区制度の創設を経て、1970年の法改正によってこの絶対高さ制限が撤廃される。これにより、技術的には可能だった超高層住居への道が、法制度的にも大きく開かれたのである。
ここで意外な事実がある。法改正を受けて誕生した日本初のタワーマンションは、大都会・東京の都心部ではなく、埼玉県与野市(現・さいたま市)に出現した「与野ハウス」(1976年竣工、高さ66メートル、22階建て)である。 東京ではなく埼玉の地で、日本の住居が初めて「空」を目指したという事実は、その後のタワーマンションが必ずしも都心だけの特権ではなく、広域的な都市化の象徴となることを予感させる出来事であった。
1997年、タワマン時代の幕開け
法的には可能になったものの、黎明期のタワーマンションはすぐに普及したわけではない。特に人口過密な東京都心部においては、近隣への日照権の問題や、建設に必要な広大な敷地の確保が難しく、多くの計画が停滞を余儀なくされていたからである。
しかし、1990年代後半に歴史の潮目が大きく変わる。 バブル崩壊による地価の下落、そして政府の方針が「郊外拡大」から「都市再生(街なか居住)」へと転換したことが背景にあるが、決定打となったのは1997年の建築基準法改正である。
この改正により、マンションの廊下や階段、エレベーターホールといった「共用部分」が、容積率算定上の延床面積に算入されなくなった。これはデベロッパーにとって革命的な変更であった。同じ敷地条件でも、実質的により大きく、より高い建物を設計できるようになり、事業採算性が飛躍的に向上したからである。加えて、日影規制の緩和や、長期的な低金利政策も強力な追い風となった。
「新・住宅双六」が示した新たなゴール
こうして「制度・金融・都市計画」の条件が整った2000年代以降、湾岸エリアの工場跡地や駅前再開発地区において、タワーマンション建設は爆発的に増加する。都市機能が「水平方向」への拡大から「垂直方向」への集積へと転換した瞬間であった。
この変化を象徴するのが、2007年に新聞掲載された「新・住宅双六」(下図)である。かつて「郊外の庭付き一戸建て」一択だった人生の上がりは書き換えられ、ついに「都心の超高層マンション」が人生の新たなゴールの一つとして明確に位置づけられたのである。

(日本経済新聞 2007 年 2 月 25 日掲載)
首都圏の住宅供給史(7) -住宅政策の転換-
「作る」から「活かす」へ。フローからストックへの歴史的大転換
新築至上主義の終わりを示す「1/70」の衝撃
これまで、団地、戸建て、マンションと、「いかに新しい住宅を供給してきたか」という歴史を紐解いてきた。しかし、現代の日本の住宅政策は、これまでの拡大路線とは180度異なる、全く新しいフェーズに突入している。
それは、戦後の住宅不足を埋めるための「大量生産・大量供給(フロー重視)」から、人口減少と成熟社会を見据えた「今ある家を長く、質高く使う(ストック重視)」への決定的な転換である。これは単なる政策の変更ではなく、人口減少社会において日本が避けて通ることのできない構造的な宿命と言える。
その変化の激しさは、数字を見れば一目瞭然だ。「今ある住宅数(ストック)」に対して、「その年に新しく作られた住宅数(着工戸数)」がどれくらいの割合かを示すデータを確認したい(下図)。

(国土交通省資料 ストック社会における住宅・住環境・市場のあり方について [11]から引用)
- 1973年:約 1/15(ストック約15戸に対し1戸が新築)
- 1998年:約 1/40
- 2023年:約 1/70
高度経済成長期の1973年には、既存住宅の15軒に1軒の割合で新築が生まれていた。街のあちこちで槌音が響き、都市が新陳代謝を繰り返していた時代である。しかし、50年後の2023年には、その頻度は約1/70にまで低下している。もはや「新築が次々と建つ」こと自体が、当たり前の風景ではなくなりつつあるのだ。
これからの不動産選びのルール
この「ストック社会」の到来は、私たち個人の不動産選びのルールをも根本から変えようとしている。 これからの時代は、「新築を買えば安泰」という神話は通用しない。すでに総住宅数が世帯数を上回り、大量の空き家予備軍が存在する中で、国の政策も大きく舵を切っている。
具体的には、マンション管理の適正化を促して建物の長寿命化を図る施策や、中古住宅(既存住宅)を新築と同じ土俵で適正に評価する「イコールフッティング」の実現などが議論・推進されている。 つまり、これからの賢い住まい選びとは、「新築というラベル(築年数の浅さ)」に飛びつくことではない。その建物がいかに適切にメンテナンスされているか、将来にわたって資産価値を維持できるかという「管理状態」や「リノベーションの可能性(ストックとしての価値)」を見極める、冷徹な審美眼が求められる時代になったと言えるだろう。
今回のまとめ
住まいのトレンドを読み解く「5つの視点」
この歴史を振り返ると、住まいのトレンドは「人々の気分」だけで変わるのではなく、構造的な要因で動いていることがわかる。
- 制度の壁:区分所有法、高さ制限撤廃、容積率緩和など、法改正が市場を作った。
- 金融の力:住宅ローン制度と低金利が、庶民の購買力を底上げした。
- 都市政策:国策が「郊外拡散」から「都心回帰」へシフトした。
- 供給の論理:プレハブや再開発など、企業側が「売りやすい・作りやすい」仕組みがあった。
- 価値観の移動:「双六」のゴールは、庭付き一戸建てからタワマンへと書き換えられた。
【ミニFAQ】
Q1. 団地って、ただの「集合住宅」じゃないの?
A. 単なる箱ではない。「寝食分離(2DK)」というライフスタイルのOSを書き換えた革命的装置であった。ちゃぶ台からテーブルへ、布団からベッドへ。今の私たちの暮らしの原点は団地にある。
Q2. なぜ郊外の戸建てが「成功の証」になったの?
A. 「住宅双六」というメディアの刷り込みと、実際に買えるようになった「経済状況(ローン・所得増)」がマッチしたからである。**「みんなが持っているから自分も欲しい」**という同調圧力が、郊外の風景を均質化させた。
Q3. 区分所有法(1962年)がないとどうなっていた?
A. マンションは「資産」にならず、ここまで普及しなかっただろう。所有権が曖昧だと銀行は融資できないため、マンション購入は現金一括払いだけの、超・富裕層の道楽に留まっていた可能性がある。
Q4. タワマンが一気に増えた「黒幕」は?
A. 1997年の規制緩和(共用部の容積率不算入)が最大のトリガーである。これと「都心回帰政策」「超低金利」という3つのカードが揃ったことで、デベロッパーも購入者もタワマンへと殺到する構造が出来上がった。
参考文献:
[7] 松村秀一『箱の産業: プレハブ住宅技術者たちの証言』(彰国社)2013
[8] マンションデータPlus 分譲マンションの歴史
[9] at home 日本のタワーマンションの歴史を知ろう!
[10] nomu.com タワーマンションの歴史
[11] 国土交通省 第 62 回住宅宅地分科会資料 ストック社会における住宅・住環境・市場のあり方について
[12] 国土交通省 マンション政策小委員会(令和6年度)
[13] 国土交通省 第 62 回住宅宅地分科会資料 既存住宅(ストック)を活かす不動産流通の現場の視点から
[続く]